
屋上防水の概要

既存防水層の劣化状態や種類などの調査診断を正しく評価し、これから施工する防水材種類との適合性を判断のもと局所補修もしくは全面防水になるのかをご提案。
一番最適と思われる防水施行を有資格者の職人が神奈川県内随所まで足を運び施行しております。
必要性と利点

屋上は常に紫外線や熱にさらされ雨もたたきつけられる厳しい環境下にあります。屋上防水工事はマンションの耐久性を高め雨漏りを防ぐために不可欠です。建物内部への雨漏りを防ぎ長期的には修繕費用の節約につながります。漏水などにつながらないよう防水層への悪影響を及ばさないうちに点検や調査が理想です。日常多忙の中メンテナンスに目を向けられないこともあるかと思いますが弊社では長期耐久性のある防水工事をご提案しお手伝いいたします。
弊社施工の特徴

屋上防水の実績
当社は横浜市と川崎市を中心に、神奈川県内全域にて豊富な経験を持つ有資格者による調査と施工を行っております。各マンションの構造や既存の防水層の状態を詳細に調査した上で、最適な防水方法を提案し施工しています。これまでに多くの雨漏り問題を解決し、他社様では対処できなかった難しいケースも無事工事を納めてきました。
建物によって下地層から伝わる屋上の動きも異なり、その予測を鑑みての調査と施工も重要になってきます。長年の大規模修繕工事の経験を生かし、各不動産管理会社からも高い評価を受けマンションオーナー様に沿った防水工事を心がけています。
屋上においての弊社の防水設計
屋上防水において重要なのは既存防水層に対する正確な劣化の把握や防水材料の判断ですが、その中でも一番重要なのが漏水個所としても多い防水層の継ぎ目や立ち上がり、ドレン周りなどの端末部の処理です。既存防水層との相性を見極め、最適な材料の選定と工法で施工致します。
施工種類

当社での屋上防水には主に4つのメンブレン防水を採用しております。いずれも現状の屋上表面がコンクリートなどの保護防水なのか、防水層が露出している仕様なのかの違いでも適用できる防水施工が異なってきます。さらに既存防水層を撤去するのか、撤去せず上からそのまま被せるように施工をする被せ工法を採用するのかを選択します。
防水施工の基本は膜を張って防水性能を保つわけですが防水の施工形態としては「液状の材料を塗り膜を張る」「シート状のものを貼る」「シート状のものを液状材料で張る」の3つがあります。
その施工形態の使い分けはやはり既存の防水層の状態や屋上の利用用途によって分かれ、その施工形態から下記4つの工法を選択していきます。
①ウレタン塗膜防水

ウレタン防水は液状のウレタン樹脂を塗布し硬化させるため、屋上にある手すりや機械基礎などの固定設置物があっても連続した塗膜形成が可能なので継ぎ目のない塗膜防水をすることができます。硬化したウレタンゴムは伸縮性に富んでいるため建物の微小な動きにも追従しやすく改修工事では非常に多く施工されている防水工事です。
②塩ビシート防水
塩ビシート防水は、塩化ビニル樹脂で作られたシートを屋上に敷き詰め、シート同士を熱融着や溶剤溶着というシート同士を溶けさせて接合するため水密性が高く、接着工法では保護層なしでも系歩行が可能な防水施工です。塩化ビニル樹脂は紫外線や化学物質に強いため、メンテナンスが比較的少なくて済むというメリットがあります。
③アスファルト防水
新築では溶融アスファルト防水工事を採用する工事も多いですが、居住者がいるマンションの改修工事ではシート状アスファルトをトーチバーナーで溶かしながらあぶって貼り付けていく「トーチ工法」のほか火器を使用しない「冷工法」や「常温工法」などの工法も可能です。
トップコート
トップコートは、既存の防水層の上に塗布する施工のことを指します。トップコート自体には防水性能はほぼありませんが、防水層を紫外線や酸性雨から防御します。遮熱機能付きトップコートを使えば建物内部の冷暖房費コストを抑えたり熱によって悪影響を及ぼす劣化原因の排除も可能です。
既存防水層の種類

防水工事をするにあたって、既存の屋上防水層が「露出防水」と「保護防水(非露出防水)」とでは、基本的に今後行う防水工法が異なってきます。屋上下地の動きや構造環境、劣化状況などを総合的な考慮して施工を行っています。
既存が露出防水
ウレタンやアスファルト、塩化ビニル系シート防水などのメンブレン防水層がそのまま屋上表層にある既存防水層のことを言います。防水層が目視で確認できるため点検・メンテナンスが容易です。
一般的には防水層への物理的な衝撃が少なくすむ歩行の必要性が限られてくる屋上に採用されることがあります。改修工事では劣化度によっては既存防水層を撤去してからでなければ施工せざるを得ない屋上もあるため丁寧な調査が必要になります。


【適用可能な防水施工】
露出防水の場合は同じ工法による防水施工が望ましいです。既存がウレタン防水や塩ビシートならコストの負担が少ない密着工法も可能です。アスファルト系防水の場合であればトーチ工法のほかウレタン通気緩衝工法や塩ビシート防水も可能です。
既存が保護防水
防水層の一番上の表層を保護コンクリート(モルタル)で覆うため、その下層にある防水層自体が紫外線や熱、風雨などの影響を受けにくく耐久性にも優れている工法です。保護層の上はある程度の重歩行にも耐えることができもちろん歩行にも強く人や物が頻繁に立ち入る屋上などに適しています。

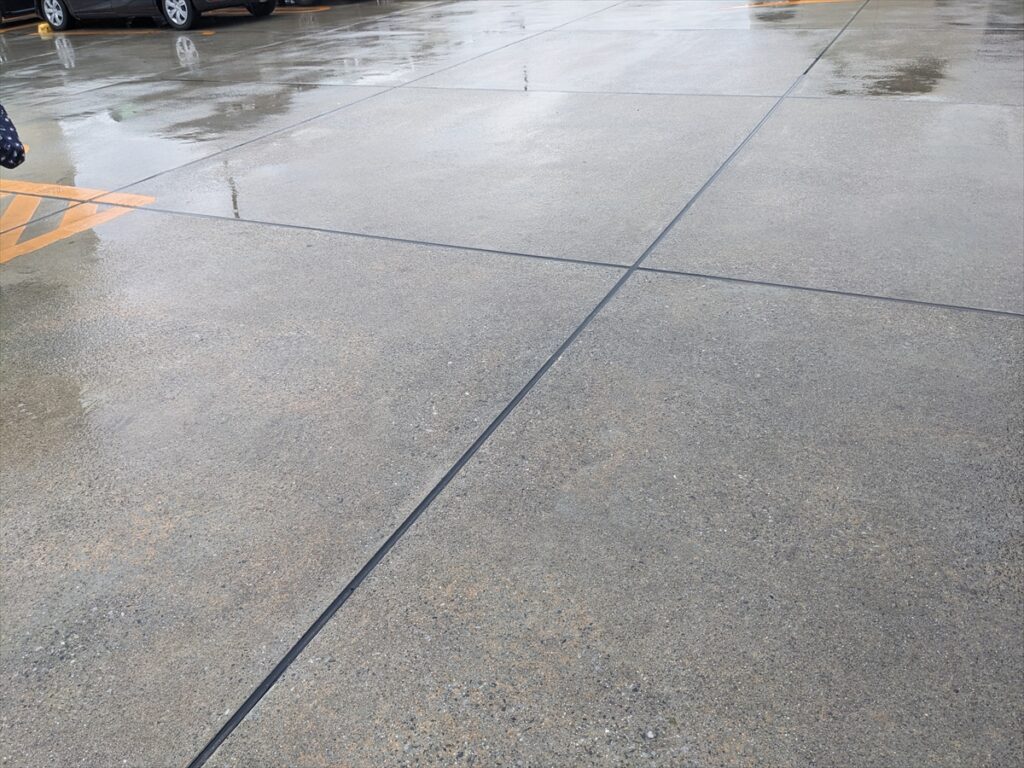
【適用可能な防水施工】
保護防水層に対する改修工事ではクラックや伸縮目地などのシール補修やポリマーセメントなどの下地調整をしてから絶縁シートを貼る仕様の防水工事が多くなります。ウレタン防水であれば通気緩衝工法や塩ビシート防水、アスファルト防水では冷工法も可能です。
屋上防水層の構造

RC造や鉄骨造りのALCマンションやビルの屋上防水の構造は一般的に下地層、防水層、保護層の3層に分けられています。RCは生コンを打設し躯体コンクリートスラブとして下地層になります。ALCはデッキ材を設置し生コンを打設する方法のほか、150ミリ厚などの厚みのあるALC版を下地層とすることもあります。その上に防水層を作って露出防水またはさらにその上に保護層を作るのか屋上によっても構造は様々です。
下地層:防水層を支える基礎となる層です。鉄筋やルーフドレンを設置し生コンを打設して平滑に仕上げてスラブを作り上げます。強度のある躯体コンクリートとして機能しますが、酸性雨で強度が脆弱化したり太陽熱による温度変化などの影響で膨張や収縮を繰り返すと亀裂が生じてしまいます。
防水層:屋上の防水機能を担う最も重要な層です。新築時の防水層としてはアスファルト防水の施工が多いですが、その他ゴムや塩ビ系のシート防水、塗膜防水などのメンブレン防水施工も採用されます。
保護層:防水層を歩行や衝撃などの物理的損傷から保護するための層です。歩行や設備の設置などによる防水層へのダメージを防ぎます。保護層は熱膨張などの伸縮によるクラック防止をするため伸縮目地を設置し、建物への重量的影響を考えてシンダーコンクリートや人工軽量骨材コンクリートで敷設します。
調査診断

建物の全体構造を把握しながら、劣化や雨漏り箇所の傾向が強い取り合い箇所を中心にひび割れ・継ぎ目などからの漏水や下地からの膨れ、保護コンクリートのシンダー目地の劣化、立ち上がり端末部の劣化などをチェックし、雨・風・紫外線などの自然環境や物損的衝撃、取り合い部などの躯体の動きなどからくる劣化要因を目視や指触で調査します。
おもな調査・検査項目
- 目視調査:ひび割れ、膨れ、浮き、排水不良などの目視による確認
- 打診検査:ハンマーなどで打診し、防水層の浮きや剥離などを確認
- 水張試験:屋上やベランダ内に水を張り漏水試験をします。
- 漏水調査:屋内に漏水がないか確認
- 材料調査:既存の防水材料の種類を確認

